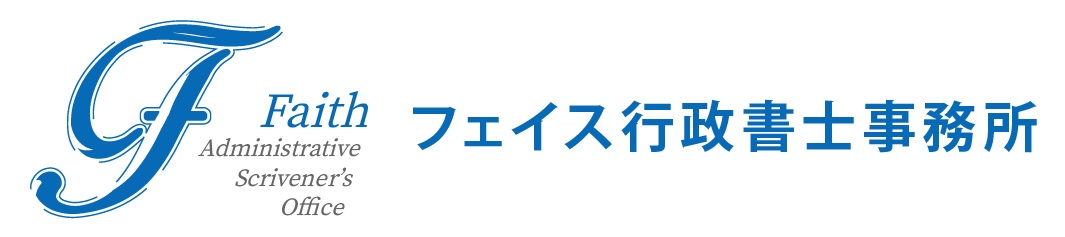任意後見制度について、他の制度との違いも含めて解説します
ご自身の将来やご家族の安心のために、事前に準備をしておきたいと考える方が増えています。任意後見制度は、そのようなニーズに応える選択肢の一つです。
どのような状況で選択すべきか、何ができるか、そして他の制度との違いについて詳しくご説明します。
目次
任意後見制度とは?
任意後見制度は、ご本人が元気なうちに、将来認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、誰に、どのような支援をしてもらうかを事前に決めておく契約です。
ご本人(委任者)が、将来、自分の生活や財産管理、医療・介護に関する契約などを代理してもらう人(任意後見人)を事前に選び、その内容を公正証書で契約しておきます。実際に判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、この契約の効力が生じ、任意後見人が活動を開始します。
こちらのリンクもご参照ください。
どのような状況の時に選択すべきか?
任意後見制度は、以下のような状況を想定している方におすすめです。
- 「もしも」の時に備えたい方:
- 現在、健康で判断能力に問題がないものの、将来的に認知症や病気などで判断能力が低下する可能性に備えておきたい方。
- ご自身の意思で、誰に、何を任せるかを具体的に決めておきたい方。
- 信頼できる人に任せたい方:
- 配偶者、子ども、兄弟姉妹、親しい友人など、特定の人に財産管理や介護の手続きを託したいと考えている方。
- 裁判所が選任する法定後見人ではなく、ご自身で選んだ人に任せたいという明確な意思がある方。
- 自身の生活や財産に関する希望がある方:
- 特定の介護施設に入居したい、延命治療に関する希望がある、特定の財産をどのように使ってほしいなど、具体的な希望がある場合。
- 家族に負担をかけたくない方:
- ご自身の判断能力が低下した際に、家族が財産管理や医療・介護の手続きで困らないように、事前に手立てを講じておきたい方。
- 相続対策と合わせて検討したい方:
- 遺言書と組み合わせることで、生前から死後までの一連の財産管理・承継をスムーズに進めたい方。
任意後見制度によって何ができるか?
任意後見契約によって、任意後見人は主に以下のことをご本人に代わって行うことができます。
- 財産管理に関する事務:
- 預貯金、有価証券、不動産などの財産の管理、運用、処分
- 年金や医療費、公共料金などの支払い
- 税金や相続に関する手続き
- 不動産の賃貸借契約や売買契約の締結・解除
- 生活・療養看護に関する事務:
- 介護サービスの利用契約や費用の支払い
- 医療機関への入院契約や医療費の支払い、治療方針への同意(ただし、身体介護や医療行為そのものはできません)
- 介護施設や老人ホームへの入退所契約、費用の支払い
- 生活費の管理や日用品の購入
任意後見人ができないこと
- 医療行為や身体介護の実行: 医療行為や直接的な身体介護はできません。これらに関する契約の代理は可能です。
- 遺言書の作成や変更: 任意後見人がご本人に代わって遺言書を作成したり、変更したりすることはできません。
- 婚姻・離婚、養子縁組などの身分行為: これらはご本人の一身専属的な行為であり、代理できません。
成年後見制度(法定後見制度)との違い
| 項目 | 任意後見制度 | 成年後見制度(法定後見制度) |
| 利用開始時期 | ご本人の判断能力が十分なうちに契約する。 | ご本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申し立てる。 |
| 後見人の選任 | ご本人が事前に選任する (任意後見人)。 | 家庭裁判所が選任する (親族が選任されるとは限らない)。 |
| 支援内容 | ご本人が契約で自由に定めることができる。 | 法律で定められた範囲での支援(ご本人の判断能力の程度に応じて)。 |
| 費用 | 契約締結時の公正証書作成費用、任意後見監督人への報酬など。 | 申立て費用、鑑定費用(必要な場合)、後見人への報酬など。 |
| 柔軟性 | 比較的柔軟に、ご本人の意思を反映できる。 | 法律に基づき画一的になりがち。 |
| 監督 | 任意後見監督人が監督する。 | 家庭裁判所が直接監督する。 |
ポイント: 任意後見制度は「事前の準備」、法定後見制度は「事後の対応」という大きな違いがあります。ご自身の意思が反映されやすいのは任意後見制度です。
信託(家族信託など)との使い分け
任意後見制度と信託(特に家族信託)は、どちらも財産管理を目的としますが、その目的や機能が異なります。 上手に組み合わせることで、よりきめ細やかな設計が可能です。
信託(家族信託)
- 目的: 特定の財産(不動産、金銭など)を、特定の目的のために、特定の者に管理・運用・処分してもらう制度。特に、「自分が認知症になった後も、この財産はこの目的で使ってほしい」「自分の死後も、この財産はこういう形で次の世代に引き継いでほしい」 といった財産の「承継」や「活用」に重点を置く場合に有効です。
- できること:
- 特定の財産を、ご自身の判断能力に関わらず、決まった形で管理・運用してもらえる。
- 自身が亡くなった後の、さらに次の世代への財産承継の仕組みを構築できる(二次相続以降の指定)。
- 共有不動産の管理などをスムーズにできる。
- できないこと:
- 財産以外の「生活・療養看護に関する事務」(介護サービスの契約など)はできない。
- ご本人の判断能力が低下した後の、包括的な代理権を付与することはできない。
使い分けと組み合わせ
- 信託が有効な場合:
- 特定の不動産や預貯金だけを、特定の目的(例:孫の教育資金、配偶者の生活費など)のために管理・運用してほしい。
- 自分が認知症になっても、事業用不動産を滞りなく管理・売却してほしい。
- 自分の死後、遺言では指定できない次の世代への財産承継の仕組みを作りたい。
- 任意後見制度が有効な場合:
- 自分の生活全般(介護サービス、医療、施設の入退所など) に関する契約や手続きも任せたい。
- 自分の財産全般を包括的に管理・運用してほしい。
- 信託ではカバーできない、ご本人の意思決定を伴う各種契約の代理が必要。
最適な組み合わせ:
多くの場合、任意後見制度と信託は補完関係にあります。
- 信託で特定の財産を特定の目的のために「縛り」、その管理・承継の仕組みを作っておく。
- 任意後見制度で、信託ではカバーできない生活・療養看護の事務や、信託の対象外の残りの財産全般の管理を任せる。
これにより、ご自身の将来に対する不安をより包括的に解消し、ご自身の希望を実現するための盤石な体制を築くことができます。
任意後見制度は、ご自身の「もしも」に備え、尊厳あるセカンドライフを送るための大切な選択肢です。ご自身の状況や希望に合わせて、どの制度が最適か、または複数の制度を組み合わせるべきかを、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談しながら検討することをおすすめします。
投稿者プロフィール

-
1980年生まれ。若い頃はしがないバンドマンでヴォーカルをしていた。
不動産会社に勤務する傍ら、お酒を止めたことを機に39歳から勉強を始め、宅建を皮切りに管理業務主任者、簿記2級、行政書士と資格取得を通じてステップアップし、開業に至るという変わった経歴を持つ。
最新の投稿
 お知らせ2025年7月5日任意後見制度について、他の制度との違いも含めて解説します
お知らせ2025年7月5日任意後見制度について、他の制度との違いも含めて解説します 遺言・相続(行政書士)2024年9月23日不動産の管理行為に見る、生前対策の重要性
遺言・相続(行政書士)2024年9月23日不動産の管理行為に見る、生前対策の重要性 お役立ち情報(不動産)2024年9月19日賃貸募集・ソシエ北大阪1番館 321号室
お役立ち情報(不動産)2024年9月19日賃貸募集・ソシエ北大阪1番館 321号室 お役立ち情報(不動産)2024年9月6日賃貸募集・朝日プラザヴェルデュール大正三軒家 307号室
お役立ち情報(不動産)2024年9月6日賃貸募集・朝日プラザヴェルデュール大正三軒家 307号室